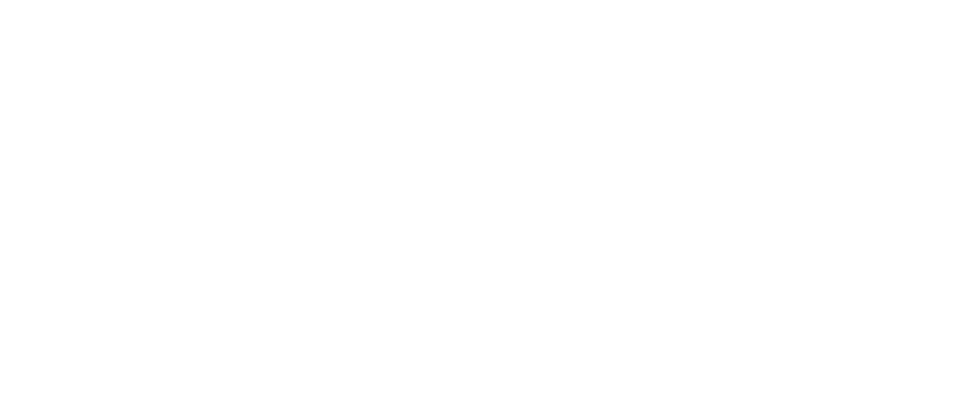
月別アーカイブ: 2025年11月
谷崎軌道の雑学講座
皆さんこんにちは!
神奈川県横浜市を拠点に軌道工事などを行っている
谷崎軌道、更新担当の中西です!
~軌道の未来~
近年、鉄道の軌道工事にも大きな変化が起きている。
AI、ICT、ロボット化、そしてカーボンニュートラル化。
軌道工事は“重労働の世界”から、“データと技術の世界”へと進化を続けている。
1. ICT施工の導入
近年、軌道整正機(マルチプルタイタンパー)には自動制御システムが搭載され、
測量データを基にレール高低や通りを自動で調整できるようになった。
これにより、作業時間の短縮と精度の安定化が実現している。
また、3Dレーザースキャナで現況をデータ化し、更新計画を自動で立案する試みも始まっている。
人の経験をデジタルで補完することで、技術の継承が加速している。
2. 保守の効率化と予知保全
従来は「壊れてから直す」だった保守が、「壊れる前に直す」予知保全へと進化している。
列車に搭載したセンサーでレール振動を常時監視し、わずかな変位をデータで検出。
異常が発見される前に、保守チームが現場対応を行う。
これにより、事故リスクの低減だけでなく、夜間工事回数の削減・作業員の負担軽減にもつながっている。
3. 環境と人材の課題
軌道工事は重労働であり、夜勤中心のため人材確保が課題となっている。
その一方で、CO₂排出削減・省エネ施工・リサイクル材利用など、環境面の改善も急務である。
-
廃バラストの再生利用
-
低騒音機械の導入
-
電動建設機械・ハイブリッド車両の採用
-
作業時間短縮によるエネルギー削減
現場の環境負荷を減らしつつ、安全で働きやすい軌道工事を目指す動きが進んでいる。
4. 若手育成と技術継承
熟練技術者の引退が進む中で、若手育成が最重要課題である。
経験に頼る要素をデータ化し、「なぜこの高さなのか」「なぜこの順序で組むのか」を可視化することで、
技能の“感覚”を次世代へ伝える取り組みが始まっている。
研修センターではVR施工訓練やシミュレーター教育も導入され、夜間現場に近い環境で安全教育を行っている。
5. まとめ
軌道工事は、長年「重くて厳しい仕事」と言われてきた。
しかし今、その姿は大きく変わろうとしている。
人と機械が共に支え合い、データと経験が融合する次世代の軌道技術へ。
変わらぬ使命はひとつ。
——「列車を安全に走らせる」。
その一点のために、軌道技術者たちはこれからも黙々と線路を整え続ける。
谷崎軌道の雑学講座
皆さんこんにちは!
神奈川県横浜市を拠点に軌道工事などを行っている
谷崎軌道、更新担当の中西です!
~夜間軌道工事の現場~
鉄道の軌道工事の多くは、列車が走らない深夜に行われる。
「終電から始発までの間に行う夜間軌道工事」は、限られた時間と厳しい条件の中で行われる最も緊張感の高い現場だ。
1. 夜間工事の時間制約
夜間軌道工事の平均作業時間は約3〜4時間。
この間に重機搬入・施工・検査・撤収までを完了し、始発列車が通れる状態に戻す必要がある。
1分でも遅れれば、ダイヤ全体に影響が出る。
そのため、工程表は「分単位」で作成される。
2. 現場の安全管理
夜間は視界が悪く、騒音規制もあるため、昼間とは違う安全配慮が求められる。
-
作業区域を明確に区分し、赤色灯・標識で可視化
-
作業員は反射ベスト・LEDヘッドライトを装着
-
線路立入前後に保安係による列車確認を必ず実施
-
工事指揮者・保安係・連絡員の三者確認を徹底
現場では「声を出す」「確認を怠らない」文化が徹底しており、暗闇の中でもチーム全体が一体で動く。
3. 精度確保のための測定技術
暗闇の中で精度を出すために、最新の測量機器とICT技術が活用されている。
トータルステーションでレール高低を自動計測し、タンパー機がバラストを自動調整する。
これにより、夜間でも白昼同等の精度が確保できるようになった。
しかし最終的な微調整は、人の手で行う。
通り・高低・ゲージを最終確認し、誤差1mm以内に収める。
この“人と機械の協働”が夜間軌道工事の本質である。
4. 施工後の確認と始発への責任
工事終了後は必ず「検測列車」または「試運転車両」による走行確認が行われる。
これで異常がなければ、始発列車を通すことが許可される。
夜が明けるころ、工事区間を列車が走り抜けていく瞬間に、現場全員の緊張が解ける。
5. まとめ
夜間軌道工事は、短時間・高精度・安全管理という三重のプレッシャーの中で行われる。
その1回1回の積み重ねが、日本の鉄道の「始発が必ず動く」という信頼を支えている。
見えない夜の努力こそ、鉄道インフラの真価を形づくっている。
谷崎軌道の雑学講座
皆さんこんにちは!
神奈川県横浜市を拠点に軌道工事などを行っている
谷崎軌道、更新担当の中西です!
~レールとまくらぎの更新工事~
鉄道の軌道は、長年の走行によって摩耗・変形・劣化が進む。
特にレールとまくらぎは、列車重量を直接受けるため、定期的な更新が欠かせない。
この回では、軌道の更新工事について詳しく解説する。
1. レールの劣化と交換サイクル
レールは鉄製でありながら、日々の荷重・気温変化・摩擦で確実に劣化していく。
主な劣化原因は以下の通りである。
-
表面摩耗・波状摩耗
-
鋼材内部の微細き裂
-
継目部の打音疲労
-
熱伸縮による応力集中
特に曲線区間では摩耗が早く、直線の約1.5倍の頻度で交換が必要になる。
一般的に、使用期間は20〜30年が目安だが、近年は高強度鋼レール(60kgレールなど)の導入で寿命が延びつつある。
2. まくらぎ更新とバラスト整備
まくらぎは、レールを支える縦材で、荷重をバラストへ分散させる役割を持つ。
以前は木製が主流だったが、現在ではコンクリート製(PCまくらぎ)が主流となっている。
更新作業では、以下の工程が行われる。
-
既設レールの一部撤去
-
まくらぎ引抜き(専用機使用)
-
新品まくらぎ挿入・通り合わせ
-
レール復旧・締結装置調整
-
バラスト整正
作業は夜間の限られた時間で行われるため、専用の軌道機械(マクラギ交換機、バラストタンパー)が投入される。
これにより、1夜で数百メートル規模の更新が可能となる。
3. 長寿命化のための工夫
近年の軌道更新工事では、単に交換するだけでなく、「次の交換までを長く保つ」ための工夫が行われている。
-
防錆塗装による金属劣化防止
-
締結装置(ファスナー)の高弾性化
-
バラストの粒度・配合の最適化
-
レール溶接継目の削減による応力低減
また、打撃音や振動を抑えるための「防振軌道」「弾性まくらぎ」も導入が進んでおり、都市部では騒音対策の要として機能している。
4. 更新工事の難しさ
軌道更新は、運行に支障を与えず施工することが求められるため、緻密な段取りが不可欠。
施工前には詳細な列車ダイヤ調整、資材搬入ルート確保、作業員配置計画が策定される。
1本の列車が遅れるだけで作業時間が30分短くなることもある。
そのため、現場では「秒単位の工程管理」が行われている。
安全確認・測定・締結・撤収のすべてが計算され尽くしており、その緊張感は他業種の工事とは一線を画す。
5. まとめ
レールとまくらぎの更新は、鉄道の“血管と骨格”を入れ替えるようなものだ。
膨大な重量・精度・時間制約の中で、安全と耐久性を両立させる。
谷崎軌道の雑学講座
皆さんこんにちは!
神奈川県横浜市を拠点に軌道工事などを行っている
谷崎軌道、更新担当の中西です!
~軌道工事とは何か ~
私たちが毎日乗っている鉄道は、時速100kmを超える高速で人と物を安全に運び続けている。
その足元を支えているのが「軌道工事」という分野である。
鉄道工事の中でも軌道は、構造物でもあり精密機械でもあり、わずか1ミリの誤差が安全性や乗り心地に影響する。
本稿では、軌道工事の基本構造、施工工程、求められる精度、そして現場の実際について解説する。
1. 軌道の役割と基本構造
鉄道の軌道は、列車の走行を支える最も重要な部分であり、以下のような層で構成されている。
-
レール(鋼製。車輪を受ける)
-
まくらぎ(レールを保持し荷重を分散)
-
バラスト(砕石。衝撃吸収・排水機能)
-
道床(地盤。列車荷重を支える基層)
この各層が一体として働くことで、列車の巨大な重量を支え、かつ安定した走行を実現している。
軌道工事とは、これらの要素を設計通りに構築し、狂いなく整える作業の総称である。
2. 軌道工事の種類
軌道工事には目的に応じて複数の種類がある。代表的なものは以下の通り。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 新設軌道工事 | 新線建設や延伸区間の敷設 |
| 更新工事 | 老朽化したレールやまくらぎの交換 |
| 改良工事 | 線形改良、騒音・振動対策など |
| 軌道整正工事 | レールの高さ・方向・通りの補正 |
| 軌道保守 | 日常・定期点検、部分補修 |
軌道工事の多くは、列車の運行を止められないため、夜間や終電後に行われる。
作業時間はわずか3〜4時間。その間に重機を搬入し、レール交換、バラスト整正、機器撤収まで完了させなければならない。
この「限られた時間と高精度」が軌道工事の最大の特徴である。
3. 軌道工事の施工フロー
典型的な軌道更新工事の流れを見てみよう。
-
現地測量(軌道中心・高低・通り測定)
-
既設レール撤去
-
まくらぎ交換
-
新レール据付・接合(溶接またはボルト締結)
-
バラスト撒出し
-
軌道整正(タンパーによる高さ・方向調整)
-
通り確認・試運転
-
検査・引渡し
どの工程にも“基準値”が存在し、たとえばレール通りは±1mm、高低差は±2mm、ゲージ(軌間)は1067mm±2mmといった精度が求められる。
これを暗闇の中、重機と人の連携で実現するのが軌道技術者の腕の見せ所だ。
4. 軌道工事における精度管理
軌道工事で最も重要なのは、精度の維持である。
現場では測量機器(トータルステーション、レールゲージ、レベル)を用いて、施工中・施工後の通りを逐次確認する。
また、最近ではICT施工が導入され、3Dデータとレーザー測量で自動整正が可能になりつつある。
しかし、最後の「1mm」を決めるのは人の感覚である。現場監督や軌道班長の経験が、最終の仕上がりを左右する。
5. 安全と連携
軌道工事は、列車の運行ダイヤに直結するため、安全と時間厳守が絶対条件である。
作業指揮者・保安要員・重機オペレーターが密に連携し、作業区域に列車が進入しないよう、徹底した保安管理を行う。
1つの確認漏れが重大事故に直結するため、「ダブルチェック」「声出し確認」が徹底されている。
6. まとめ
軌道工事は、単なる「線路の工事」ではない。
1ミリ単位の精度と、数十人が一体となる作業の中に、日本の鉄道の信頼性が宿っている。
安全・精度・時間。この3つを守り抜く現場の努力こそが、見えないところで社会を支えているのである。




