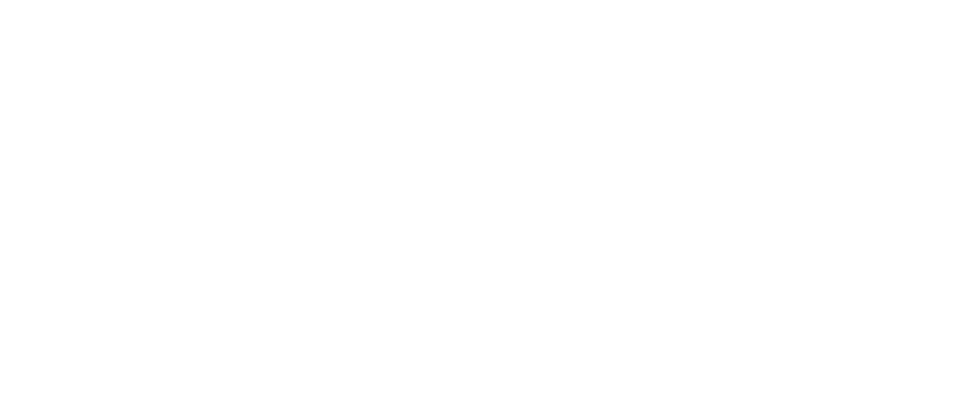
谷崎軌道の雑学講座
皆さんこんにちは!
神奈川県横浜市を拠点に軌道工事などを行っている
谷崎軌道、更新担当の中西です!
~変遷~
1|創成期:人力中心の保守と木まくらぎ(〜1950年代)
鉄道初期の軌道は、木まくらぎ+犬くぎ、短レール(継ぎ目多数)、砕石道床というシンプルな構成。
施工・保守はつるはしや道具による人力作業が中心で、継ぎ目の段差や道床の沈下に対してこまめな手入れが必要でした。
-
レールは25〜40kg級が主流、継ぎ目ジョイント多数
-
道床締固めも手突き、軌道整正は職人の勘に依存
-
軌匠の力量が乗り心地と安全を支える時代
2|機械化・標準化の黎明(1960〜70年代)
高度経済成長で輸送量が増加し、機械化保守が普及。
-
**マルチプルタイタンパ(マルタイ)**による道床突固め
-
レール削正車で波状摩耗を補正し、騒音・振動を低減
-
コンクリートまくらぎが普及、レールも50kg級へ重軌条化
-
保守周期・品質を標準手順で管理する文化が確立
3|ロングレールと高規格化(1980〜90年代)
列車速度・重量の向上に合わせ、軌道は高規格化へ。
-
**ロングレール(CWR:ロング溶接レール)**で継ぎ目を極少化、乗り心地・保守性が向上
-
分岐器のユニット化・プレハブ化で夜間短時間(終電〜初電)工事に対応
-
バラストクリーナーや道床交換列車で一括更新が可能に
-
幾何形状(通り・高低・カント)の測定車による定量管理が一般化
4|スラブ軌道と高速鉄道の時代(1990〜2000年代)
高速化・都市部の保守窓縮小に応えるため、バラストレス(スラブ)軌道が拡大。
-
コンクリートスラブ上に弾性支持材でレールを固定し、幾何安定性・保守省力を両立
-
都市高架・トンネル・高架橋でのLCC(ライフサイクルコスト)最適化
-
騒音・振動対策として弾性まくらぎ・防振まくらぎ・浮上げ床など弾性系の工夫が進展
-
軌道と構造物の縦・横荷重連成を考慮した設計・施工が当たり前に
5|夜間短時間・安全最優先の運用工学(2000〜2010年代)
需要増とダイヤ過密で、**工事時間は“短く・安全に・確実に”**が大命題。
-
パネル化(道床+まくらぎ+レールをパネルで交換)、分岐器の総替えも一夜施工へ
-
フラッシュバット溶接やテルミット溶接の品質管理を厳格化(前後応力管理・超音波探傷)
-
リスクアセスメント、KY(危険予知)、列車防護・閉塞手続きの徹底
-
作業員の保護具・動線設計、重機接触防止のセーフティセンサー導入
6|DX・センシング・予防保全(2010年代〜)
“壊れてから直す”から“壊れる前に手を打つ”へ。
-
軌道検測車の高頻度走行とAI解析で不良トレンドを早期検知
-
レール頭頂の画像・レーザー計測、道床沈下の加速度・ひずみセンシング
-
BIM/CIMで施工前の干渉確認・数量精度を高め、出来形も3Dで記録
-
ドローン・地上LiDARで盛土や法面の健全度を面的に把握
7|レジリエンスとサステナビリティ(現在〜)
気候変動・災害多発時代に合わせ、レジリエンス重視の設計・保守へ。
-
豪雨時の排水能力・道床目詰まり対策、土圧・洗掘に強い線形補強
-
遮音壁・防振、再生材バラスト・長寿命部材の採用で環境負荷低減
-
ライフサイクルでCO₂を把握するカーボンマネジメント
-
労働力不足に備えた省人・省力ツール(自動計測、遠隔重機、ロボット)
8|タイムラインで一気に把握
-
〜1950s:人力保守/木まくらぎ/短レール
-
1960–70s:機械化保守の普及(マルタイ・削正)/コンクリートまくらぎ
-
1980–90s:ロングレール/一括更新機械/幾何形状の定量管理
-
1990–2000s:スラブ軌道/防振・騒音対策/LCC志向
-
2000s–2010s:夜間短時間施工・ユニット化/安全マネジメント高度化
-
2010s–:DX・センシング・予防保全/レジリエンス・サステナブル
9|現場を強くする“いま”のキーワード
-
データ連携:検測→計画→施工→出来形→運転の一気通貫
-
モジュール化:パネル・分岐器ユニットで“夜間一発仕上げ”
-
応力管理:CWRの温度応力・座屈対策の見える化
-
排水設計:バラストの性能は水で決まる。ドレーンと清掃をセットで計画
-
人×機械の安全設計:接近警報、立入管理、重機の自動停止
まとめ
軌道工事は、
-
人力の時代から機械化・標準化、
-
ロングレールと高規格化、スラブ軌道とLCC志向、
-
そしてDX・予防保全・レジリエンスへ。
目的は一貫して「安全・安定・快適な走行」。
手段は進化し続け、夜間の短い時間でも高品質に仕上げる“運用工学”が磨かれてきました。これからの軌道工事は、データとモジュール、そして人の熟練を組み合わせたしなやかなインフラづくりへ進みます
谷崎軌道では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
神奈川県横浜市を拠点に軌道工事などを行っております。
私たちが最も大切にしているのは、「安全意識」と「チームワーク」。
ぜひ求人情報ページをご覧のうえ、ご応募ください。
皆さまのご応募を心よりお待ちしております!





